| 写 真 |
簡易説明 |
| 物々交換時代 |
  |
古代人々は物々交換しながら生活を営む |
| 物品貨幣時代 |
   |
物資の交換に伴う不便を取り除くための代替物が、交換に用いられるようになった。貝・家畜・鼈甲 |
| 日本貨幣(公鋳貨幣)の誕生 |
  |
飛鳥〜平安時代
我国最初の公鋳貨幣として「和銅開珎」を発行
以後、計12種の公鋳貨幣を発行する。
皇朝十二銭と呼ばれる。
|
| シルク(絹)の時代 |
 |
皇朝十二銭は廃止され、モンゴル帝国の繁栄に伴い、シルクが代用される。 |
| 中国銭(渡来銭)の使用 |
  |
鎌倉〜室町時代
中国貿易により流入した銭をそのまま自国貨幣として通用した。
しかし経済拡大に伴い貨幣が不足、私鋳銭(鐚銭(びたせん))が横行。 |
| 秤量貨幣 |
  |
戦国時代
中国(明)が銅銭流出禁止、金山・銀山の開発、戦費調達などにより
砂金や灰吹銀での取引が活発化する。 |
| 領国貨幣の時代 |
  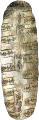 |
戦国〜安土桃山時代
各地の大名が領内流通を目的とした地方貨幣。
武田信玄の「甲州金」豊臣秀吉の「天正大判」などが有名。
「壱両」165g |
| 貨幣制度の成立 |
   |
江戸時代
徳川幕府は全国通用貨幣制度を制定、貨幣発行権独占と貨幣様式の統一を図った。
渡来銭・鐚銭の使用は禁止。
金1両=銀50匁=永1貫文=鐚4貫文
|
| 貨幣の改鋳 |
   |
江戸時代には、経済状況に応じて度々貨幣の改鋳が行われた。
これにより流通量の増大・物価上昇に対処しようとした。
貨幣量の適正化を目的としたが、幕末にかけて、財政窮乏を補うため質を落とす改鋳が度々行われ、慢性的なインフレを引き起こした。
江戸末期の「万延小判」は大きさも極端に小さく、純金量も慶長小判の約1/8。
公定相場 金1両=銀60匁
計量貨幣「一朱銀」の発行。小判一両=一朱銀8 |
| 藩札紙幣の流通 |
   |
藩札は、幕府鋳造の三貨との兌換を前提として発行された。
金札、銀札、銭札などがあり、正貨との引き換えに際しては非常に厳しい制限が課されていた。 |
| 通貨の近代化 |
   |
明治4年(1871)に明治政府公布「新貨条例」により、「円」の採用。
洋式貨幣と貿易用の一円銀貨。10進法単位、円・銭・厘。
金本位貨幣、銀・銅貨を補助貨幣。
1882年「日本銀行」開業
本位制の確立・紙幣の統一
|
| 臨時補助通貨 |
   |
1917年、大量の金流出、第一次世界大戦をうけ、金本位制の廃止。
金兌換銀行券も廃止。
日中戦争・太平洋戦争による、銀・銅・ニッケルの回収に伴い、代替え金属での「臨時補助貨幣」や少額紙幣などを発行。
アルミニウム・青銅・黄銅・スズ
|
| 管理通貨制度 |
 |
1942年、日本銀行法により管理通貨制度へ
明治30年〜昭和62年まで貨幣法が有効であったため、昭和62年までの貨幣は臨時補助貨幣と呼ばれる。(昭和63年に貨幣と改正)
現行貨幣。
|
| クレジットカード決済 |
 |
クレジットとは信用という意味である。
1950年、アメリカダイナーズクラブカードが発祥。日本は1960から。
高額紙幣を持たなくても買い物ができることから非常に便利であり、急速に広まった。分割払い、ボーナス払い等サービスも多い。
一方で、使いすぎ、スキミング・フィッシングといった詐欺、番号流出など問題や犯罪被害も多い。 |
| 電子マネー化 |
 |
電子マネーには2タイプある。あらかじめ入金するプリペイド型、後払い請求がポストペイ型である。クレジットカードは審査やサインなど不便な点もあった。その点、瞬時に支払いのできる電子マネーが拡がりつつある。有名なものでWAON・nanaco・Edy・suicaなど。 |
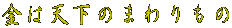

|